'!' は論理演算子 Not です。
「日記にあらず」と読んでください。
Category: ニュース関連
■ 核危機
北朝鮮が「核実験をやるぞ」と言って1週間で実行したと思ったら、国連では中国も賛成してあっという間に制裁決議が採択された。一線を越えたとたんに極東を巡る国際情勢は急転直下だった。変化が早すぎて着いて行くのが大変だけど、まあここまでは予想の範囲。
さて、これからどうなってしまうのだろう。
経済封鎖で政権が倒れないのはキューバで実証済みである。まして何百万もの国民が餓死しても意に介さない政権なら尚更のこと。
今のアメリカに二正面作戦をする余裕が無い以上膠着状態が続くのだろう。
時間稼ぎは北朝鮮の望むところでもあるはずだ。その間に核開発を進められるのだから。
多分無いだろうけど八方丸く収めるには中国が引導を渡して金正日の首をすげ替えることだ。
たとえ新政権が中国の傀儡だったとしても今よりずっとましだろうからアメリカも承認するだろう、多分。中国だって北朝鮮という緩衝地帯があれば良い訳だから独自の軍隊を持ったまま、中国の権益を維持したままなら、韓国とのゆるい連邦制を認める可能性すらある。
しかし現実的には中国にもこれは難しいんだろうな。中国が金正日に「亡命しなさい」なんて言ったとたんに暴発する危険がある。下手をすれば北京にミサイルが飛んでいく可能性だってあるわけで。
どうしたら引導を渡せるんだろう。
米中が密約を結んだ上で大芝居を打つ。
アメリカは軍事オプションを容認する国連決議を提出し、ロシアは棄権するが中国の拒否権発動で可決されず。
それでもアメリカは多国籍軍を編成、大艦隊を出動し、38゜線には機甲部隊を集結、空には撃墜される前提の無人偵察機を飛ばして軍事危機を煽る。
いや、ここで北朝鮮を暴走させてはいけない。「戦争の意思はない」「侵攻はしない」と繰り返すアメリカ。しかし船舶の航行は完全に阻止して海上封鎖状態。
ここで中国の出番である。アメリカの侵攻を阻止するという名目で数十万規模の人民解放軍を北朝鮮に派兵。北朝鮮も馬鹿じゃないから始めは拒否するだろう。でもアメリカの軍事圧力と中国の説得で何とか納得させる。ここが重要。
結果、見掛け上米中が直接対峙する。でも本当は米中合作。
国境や海岸線の守りは万全。将軍の身辺は近衛兵ががっちり固めている。その近衛兵の一人に偽情報を流す。
「今夜将軍様を殺そうとするアメリカのスパイが侵入する。それを射殺したらお前は出世間違い無しだぞ。」
その夜。金正日のベッドの電話が鳴る。
「米軍のピンポイント攻撃です。すぐに退避してください!!」
裸足で部屋から飛び出した将軍に銃弾が発射される。幸い弾は外れた。撃ったのは偽情報を掴まされた兵士だったが、すぐに他の兵士に射殺される。
裏切り者がいる。近衛兵だけでは危ない。こうして将軍の身辺にも中国軍の護衛が付き添うことになる。
中国との直接対決はアメリカも望まない。一触即発の軍事状況のなか、これで手が出せまいと有頂天になる金正日に向かって中国の将軍が言う。
「車をご用意しました。同道願います。」
あ、暴走したのは私でした。
不謹慎な妄想です。
■ 蘇生
昨年末から通信が途絶えていた小惑星探査機「はやぶさ」との交信が回復したもよう。まずはめでたい。
だけど今の通信レートが32bps ってのがなんか「瀕死ー」って印象だよ。
これでも1ビットや8ビットよりましだけど、一秒間にたった4バイトのデータしか送れないんだものなぁ。漢字にしたら2文字ぶんですぜ。ネットの回線が遅いなんて文句言ってたらばちがあたるよ。
1月末にはビーコンを受信。意外と早い回復だったようだ。ただし、完全に電源が落ちて、極低温にも曝されたのだろう。ダメージも大きいようだ。
コンピューターがリセットされた訳でタッチダウン前後のデータも消滅したもよう。研究者にはこの辺が一番痛かったかも。
12月の時点で姿勢制御ロケットの燃料(ヒドラジン)が機体内に漏れていたのだが、その後、酸化剤(四酸化窒素)も漏出したらしい。これ、混ざっただけで発火するっていう性質があって、エンジンの構造を単純に出来るからスラスターに使われてるんだけど、よく機体内で発火しなかったものだ。不幸中の幸いっていうか、奇跡に近いんじゃないの?
バッテリーは内部のショートで使用不能。スラスターも燃料が無くて使えない。
電力は太陽電池で賄えるそうだが、姿勢制御も兼ねることになったイオンエンジンを再始動できるかが問題。
これから時間を掛けて内部温度を上げ、ゆっくりと機体内部に残ったガスを追い出してからエンジンのテスト。ハードルは高い。帰還できれば本当の奇跡だ。
でも、その奇跡を祈っちゃうぞ。
それにしても技術的な説明を読んでると「すげーなぁ」って思う。
残っているイオンエンジンの中和剤は僅か42~44kg。これで上手くいけばだけど3億kmの距離を戻ってくるんだから(いや、地球をかすめて行くだけだけど)、すごい燃費だよなぁ。
もっとも中和剤のキセノンガスは42kgで700万円ほどするそうだが。
■ ああ、伊福部昭が亡くなってしまった
朝、ネットをチェックしていたら作曲家の伊福部昭氏の訃報が目に飛び込んできた。直腸ガンによる多臓器不全だそうである。
さすがに91歳という御歳だから天寿を全うしたと言ってよいのだろうが、ファンという以上に、敬愛する方の死去というのは黒澤明監督以来のショックである。
名も無いファンの一人ではあるが、哀悼の意をなにか形で表せないかとトップページのロゴをモノクロにした。
私が伊福部昭を知ったのは当然ながら怪獣を中心とした映画音楽からである。
力強く繰り返されるあのリズムと日本的旋律は私の中で特別なものだった。
そして、いつの間にか映画音楽に留まらず、氏の音楽そのものを愛するようになっていた。ストラビンスキーのように力強く、それでいて日本的な、それも妙に風雅ではなく(いや、風雅な曲もあるけど)土着的な、地に根の生えた生命力にあふれる響き。
特に好きなのは大編成のオーケストラを中心とした交響曲である。
映画音楽では編成の小ささや演奏時間の短さで不満が残ることもある。ああ、この音の渦にもっと浸っていたいのに。
そんな不満を満たしてくれるのが「リトミカ・オスティナータ」や「ラウダ・コンチェルタータ」や「交響譚詩」だった。
氏の曲が掛かると演奏会に足しげく通った時期もあった。
「ラウダ・コンチェルタータ」の初演を聴いたのが自慢でもあったし、「SF交響ファンタジー」の公開録音にも行った。(懐かしい! 故、平田昭彦氏が司会を勤められた。)
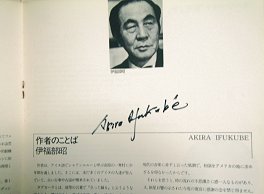
私の持っている唯一の有名人のサイン。
私はあまり物を大切に取っておく方ではないのだが、それでも演奏会の合間にロビーで一人所在無げにしていた氏からプログラムに書いて頂いたサインは数少ない宝物の一つである。
ああ、またひとつ巨星が堕ちてしまった。
合掌である。
■ 科学技術部記者のなれの果て
えーっと、ココの所ずっと暇があると「はやぶさ」関係をヲチしてるわけだけど、今回はちょっと別の角度からの話。
日経の清水正巳という編集委員のコラム。
研究の失敗に寛容な風土はできるか
掲載直後から2ちゃんねるの関連板あたりで批判が相次いで、遂に今この問題ではネット上で一番影響力のある松浦氏も噛み付いた。
件のコラムに関しては何の勉強もせずに思い込みだけで書いた記事で、読んだ直後は本当に頭に来たが、もう納まった。私の言いたいことは多くの方がいろんな処で突っ込んでいるから。 あ、これだけは書いておこう。
外国のES細胞捏造なんかと同列に語るな!
これが日経の編集委員で「日経サイエンス」の元編集長ってんだから情けないやら悔しいやら。
随分と昔、これと同じ思いをしたことがある。
発行部数、日本一の某大新聞の署名入り記事で「日本は基礎研究より応用研究に力を入れるべきだ」という論旨の記事を読んだとき。
それまで「日本は研究の成果の美味しい所だけを持って行ってしまう」と海外から批判され、外国が研究の成果を渡してくれなくなってギブアンドテイクじゃなきゃだめだと、やっと基礎研究の重要性が一般にも認知され始めた頃だ。にもかかわらずこの某大新聞は貴重な紙面を割いて「基礎研究はいらない」と言い張る記事を掲載したことに暗澹たる気持ちにさせられた。
小さなコラムとはいえ全国の人が読む新聞だから影響力は否定できない。なるほど、と納得する人も少なくはないだろう。
対して反論する場所はどこにもない。せいぜいが頑張って投書する位だが、それで記事が取り消されることはない。
ところが今回の件に関しては松浦氏も書いておられるように
という事だろう。
民主主義が(うまく機能すれば)政治家や役人が「お上」から「市民の下僕」になる様に、ネットによって情報も民主化されつつあり、メディアの人間も特権階級ではいられなくなっているってことにこの清水某は思い至らないから安易な思い込みを書いたわけだ。
ブログは簡単に炎上するが新聞社のサイトは耐火構造になってるから(^^)燃え落ちることはないだろう。
しかし、このコラムもいつかは削除される日が来るが、ネット上で大量に書かれた批判記事の幾つかは残り続けるだろう。今現在でも「清水正巳」と検索すれば本人の記事より松浦氏の記事が先に表示される。
ネットを見る人は、まず批判記事を目にしてから清水某の記事を読むわけだ。
蛇足だけれど、民主主義ってのはすごく危ういバランスの上に成り立ってる。
「十二人の怒れる男」のラストシーン。陪審で少年の冤罪を晴らしたヘンリー・フォンダか誇らしげに言う。「だから民主主義は素晴らしいんだ。」
でもね、もしその場にあんたが居なかったら民主主義で少年は死刑になってたんだよ。
陪審員の中にいつもヘンリー・フォンダがいるとは限らない。
ネットだって誘導を間違うととんでもない事になる。
ってことで、ウチも松浦ブログにトラックバック。え?縁起モノですから。
■ 危篤
今日のテレビは一日中「耐震強度偽装事件」の証人喚問。姉歯某。自己保身のためのファウルは誰でも大なり小なり犯す可能性はあるし、下請けの悲哀が解らないではないが、自分と家族の生活を守るために何百、何千の人の命を危険にさらしたことの言い訳にはならない。
それより何じゃい、あの議員の質問は。お前の意見なんか聞いてない。選挙演説じゃないんだからさっさと質問しろよ。
そんな中、昨日から待っていた「はやぶさ」関連の記者会見。勿論テレビ中継があるわけじゃ無いから「松浦晋也のL/D」だけが頼り。朝から何度もチェック。
上の記事が出る前に速報。うわぁ、だめか...
幾つかの新聞社のサイトを見る限り帰還予定が2010年に延期と云った見出しだけれど、記者会見の様子を見ると現状は、医者も手を出せない意識不明の危篤状態という感が強い。
電源が落ちてビーコンすら受信できない。地上からのコマンドも受け付けないほど姿勢を乱して回転している。
今出来るのは回転モーメントが減衰して姿勢が安定するのをじっと待つだけ。その時太陽電池パネルが反対を向いていたら...電力が回復しないで...って読めるわけだけど、確率の問題ってそういう事ですか?
確かに復旧の可能性が3分の2なら悪くはない。でもその先に待ってるのはもっときわどい運用。
スラスターが復旧しなければイオンエンジンの中和剤として積んでるキセノン噴射で姿勢を制御して帰還軌道に乗せるって超裏技。これ、車で言えばハンドルが壊れたからアクセルとブレーキでスピンターンを繰り返しながら目的地に向かうようなものだ。
つまり
可能性がある限り諦めない。この姿勢には頭が下がる。
でも運用チームの皆様、この一ヶ月へとへとだと思います。今はゆっくり休んで鋭気を養って頂きたい。
そして必ず地球圏への帰還を果たして欲しい。気長に待つとしよう。
さて、気を取り直して与太話。
この数回の記者会見の中で度々登場する「みそすり運動」って言葉。
コマの回転が落ちてきたとき大きく首を振るような動作のことなんだけど、いやー、久々に聞きました。いや目にしました。今でも使ってるんだなぁ。
初めて聞いたのは子供のころ。多分地軸が長い時間で移動するのを説明する教育番組か何か。その頃、すでに「随分古い言葉だなー」って思った。我々の世代ならやったことは無くても辛うじて「味噌を擂る」の意味を理解できるけど(それにしても「胡麻を擂る」方がまだ身近だったな。「日本一のごますり男」とか)、今の子供には何の事やら理解できないでしょ。
よほど酔狂じゃなければ自家製の味噌なんて作らないし、すり鉢だって滅多に無いよ。
こういう意味不明の言葉は解りやすい言葉に置き換えるのが良いのか、昔の生活を伝えるために残すのが良いのか?
でもロートルには「コーニング」よりは解りやすいんだけどね。
■ 苦難は続く
「はやぶさ」が正念場を迎えている。サンプル採集に成功してワーッと盛り上がったのも束の間、帰還出来るか否かの瀬戸際を迎えてしまった。
前回、トラブルそのものは致命的ではないと書いたけれど、その後状況が変わって、場合によっては致命的なことになる可能性が出てきた。
JAXA プレスリリース
松浦晋也のL/D 11月29日の記者会見の様子
そして最新の情報
YMコラム(的川泰宣教授のコラム)
って、ほとんど新しい情報が入ってないんだ。
うう、電源も落ちてますか。状況を把握するのに月曜まで掛かるんですね。あと一週間の時間との勝負って状況になってしまったのにデータが降りてこないんじゃ手の打ちようがないんだろうなぁ。
状況を整理する。
■ 今月中旬までに出発しないと地球へ帰還できないが、サンプルを安全に投下するには上旬でなければならない。
■ 3つあるリアクションホイール(ジャイロ効果で姿勢を保つ装置)のうち、2つが壊れてしまった。
■ その代替処置としてスラスター(姿勢制御用化学燃料エンジン)で姿勢を制御していた。
■ 2系統あるスラスターの主系統で燃料漏れが発生。(バルブが閉じないで噴射しっぱなしになる?)
■ 予備に切り替えるも、出力が低下して姿勢を制御できない。(配管内の凍結かバルブの詰り?)
もう一つ、「はやぶさ」の構造的前提として
■ メインエンジンと高利得アンテナの方向が(主に経済的理由から(T_T) )固定である。
つまり姿勢の制御が出来ないとエンジンを吹かしても進む方向が定まらないし、詳細なデーター通信も出来ない。運行は可能でもトラブルの原因を突きとめるには詳細なデータが必要だし、闇雲にメインエンジンを噴射すれば帰還不能な軌道に入ってしまうのは自明の理。
経済的理由で思い出したのだけれど、今回故障したのはアメリカ製リアクションホイール。国産の半分の値段で(多分)国産品より高性能だったのだと思う。コストパフォーマンスを考えれば当然の選択と言える。ただしブラックボックス。なにか問題が起こったとき構造が解らないっていうのは本当に困るのだよね。対処できない。これはウチのような末端の機械屋でも大手メーカーが中身を公開してくれない時は本当にイライラするので切実に分かる。
だから宇宙開発や自衛隊関係者が予算を無視して国産にこだわるのも理解できるけど、結局はメーカーや製造国との力関係なんだよね。アメリカは日本製のブラックボックスでも政府の圧力で強引に開けたりしてるし。
閑話休題。さらに運用上の問題として
■ 夜間は NASA にお願いして地上アンテナを借りるしかない。
NASA のアンテナだって土星のカッシーニやら火星のローバーやら、いろんなミッションで忙しい。その合間を縫って急遽使わせて、とお願いしてもあちらさんの都合だってあるわけで...。
っと、こんな中で問題を解決して12月上旬に地球に向けて発進しなければならない。
もし、タイミングを逃すと、次のチャンスは4年後になるそうである。うーーーん。
4年間、地球とはやぶさが最短距離になるのを、今の軌道でじっと待ってるって事?。
もし一週間以内に問題が改善されない場合、難しい選択を迫られることになりそうだ。
失敗に終わった火星探査機「のぞみ」が頭をよぎる。
これもスラスターの故障で予定軌道に乗れなかった。奇しくも4年後のチャンスを待っている間に太陽の巨大フレアの影響で電源回路が故障して、最終的に火星の周回軌道には到達できなかった。
良い方に考えれば今回は「のぞみ」の苦い経験を生かしてなんとか「生還」させて欲しいと願うばかりである。
■ 行け、行け、川口探検隊!
しまった、寝過ごした。
慌ててライブを見るとちょうど上昇に転じたところ。
予定より少しだけ遅れたみたいだ。
「何らかの理由により、はやぶさは上昇に転じました。」
なんて書いてあるから少し不安になる。いや、通信が途絶えてるから、地上からは「はやぶさ」が発するビーコンのドップラー偏移で降下してるか上昇してるかだけしか分からないだけなのだけれど。
暫くは待つしかない。地上アンテナもちょうどアメリカから臼田に切り替わり。前回はこのタイミングでトラブルが発生したのだが、今回は大丈夫そう。
相模原の管制室のライブ映像を眺める。8時過ぎから人が増えてきた感じ。でも表情は笑っているように見える。どうやら順調のようだ。
何度も松浦ブログを確認。
「午前8時45分
採取用の弾丸発射を確認。その後も順調。」
だそうである。
やったね!!
これを書いている午前10時半現在、「はやぶさ」は無事。そしてサンプラーホーンが何かに触れた、以上のことは判らないとしている。JAXA はあくまで慎重だけど、成功は間違いないだろう。
ハイゲインアンテナからのデータのダウンロードも始まったようだ。

プロジェクトマネージャーのお名前です。カメラが先に行って待ってたりしない、これは本当の宇宙探検なのだな。
========================================
と、安心しきって仕事に出かけて帰ってきたらちょっとヤバイことになってるみたいだ。
姿勢制御用エンジンに燃料漏れ?
うわぁ、もったいない、もったいない。トラブルそのものは致命的なものではないのだけれど、また燃料を無駄遣いしちゃった。
帰還時の姿勢制御は大丈夫なんだろうか。
■ 着陸していた!!
またまた「はやぶさ」スマソ、個人的には今年最大のイベントだから。
という訳でその後の状況がJAXAからリリースされた。
「はやぶさ」の第1回着陸飛行の結果と今後の計画について
着陸していないと予想されていたのが、実は着陸していた事は、またまた松浦氏のブログ(なにしろ本家のJAXAより情報が早くて詳しい)で知って驚いたのだが、詳細な発表を読むとかなりきわどい状況だったことが解る。
■ 「はやぶさ」は自律降下中に障害物を検知した。
これは結果的に誤動作という事なのだけれど、上記発表では「何らかの反射光を検出したため」と書かれているだけで原因が特定されていない。
もし、ターゲットマーカーが着地した時に巻き上げた砂や砂利に反応したのなら次のときも起こりうるし、地形に由来するものなら運を天に任せるしかない。
いずれにしてもセンサーの判断基準を見直す必要がある。
■ 障害物があると判断したのに緊急離脱できなかった。
今回は判断そのものが間違っていたから無事だったけれど、本当に岩などの障害物が有ったら致命的なことになりかねない。
■ 着地後、2回バウンドしている。
バウンドは予想外だったらしい。 → 「はやぶさリンク」:はやぶさ23日夜時点の現状、ミネルヴァについて
本来、着地した瞬間に弾丸を発射して舞い上がったサンプルを収集するわけだが、機体がバウンドして逃げてしまったら上手く集められるのだろうか。少々不安が残る。
■ その後、完全に着地したにも係わらず、プログラム的には既に離脱状態の制御に移っていたので離陸のための噴射をしなかった。
一つずつの判断を見れば適切なプログラムだけれど全体としては限りなくバグに近い。まあ、これに関しては新しいプログラムを送れば済むことだろうが。
でもって、ネットを見ると「着陸してて良かった」という反応が多いようだけど、
これ、「着陸」って言えるだろうか。
どちらかと言えば「不時着」だよなあ。いや、責めてるんじゃない、心配してるんだ。
もし地上からの緊急離陸命令を受け付けなかったらと思うと冷や汗ものである。
2回目の着陸も無理をしないで安全第一で。これだけデータが取れればミッションが失敗なんていう人はいないと思うぞ。
30分っていうオマケの長期滞在中に(予定では地上にいるのは1秒ほどだった)姿勢制御で元々余裕のない燃料を減らしてるし、技術試験が目的なら何としても帰って来て欲しい。
小惑星に接地した後離陸した世界初の探査機になった訳なのだが「嬉しさも中ぐらいなり」ってのが本音かな。
もう一つ、5thstarさんで紹介されている関連ネタで「はやぶさ」が緊急離脱した理由が分かった。
上記JAXAのサイトの「イトカワ」地表に投影された「はやぶさ」の影とターゲットマーカーが光っている写真(図3a)を見た上でご覧あれ。
小さい写真ではよく分からなかったけど、大きい写真を見て大笑い。
わはは、これじゃ離脱しないわけにいかない。
アメリカ人もやるな。
更についでと言っては何だけど、ペーパークラフト・サイトの端くれとしてはこれも紹介しておこう。
はやぶさペーパークラフト
■ はやぶさ
今日は「はやぶさ」の着陸。起きなけりゃ、起きなけりゃ...
朝の5時、ボーっとした頭でHayabusa Liveを開く。
おお! 「Go」が出てる。
だけど更新は10分に一度ほど。もどかしい。
しかも「午前5時40分現在、高度は約90メートルです。」のアナウンスの後は更新が止まってしまった。
なんだよぅ、ここからが肝心なところじゃんか。
最初のリハーサル降下の時も順調に降下中のアナウンスがパッタリ止まって1時間以上経ってから急に「本日のリハーサルは中止になりました」という簡単なメッセージで御仕舞いだった。
オペレーションが忙しくなると人手も予算も足りないから、広報にまで手が回らなくなるのは充分理解しているつもりだけど、一国民としては「何がなんだか訳わからん」状態にされるのは辛い。
都合の悪いことが起こると「ちょっと待っとけモード」に切り替えてるとは思いたくはないけど、勘ぐりたくもなる。
こうなると松浦ブログだけが頼り。
相模原のISASプレスルームから刻々と更新されてる。
ターゲットマーカーを投下。
「はやぶさ」が上昇に転じた。
着地したか否かは不明。
うん、うん。ターゲットマーカー投下後は直接交信が出来なくなるから何も解らないのだね。これも前日の記者会見の模様を詳細にアップされた松浦氏のおかげで手順を知ることが出来た。
でもこれって本来納税者の理解を得るために国がやるべきことじゃないか。
せめて特別なイベントの時くらい現場スタッフの負担にならないように人を派遣するとか。
って、あわわ、トラブルが発生した模様。(07:57 AM)
「はやぶさリンク」:トラブル発生
現在まで上昇は確認されていない。
アンテナの切り替え時間ってのもタイミングが悪い。
よく解らないのは現在もビーコンを受信しているのか、いないのか。
もしビーコンが途絶えたとなると最悪だけど...(08:35 AM)
おお、ビーコンは受信できてるのね。よかった、よかった。
そして地表に居る可能性も消えたようだから、なんとか修復してほしい。
ガンバレ! (09:45 AM)
とりあえずだけど、通信も回復したらしい。
着地に成功していたのか気になるところだけど判るのは明日になっちゃうのかな。それより無事が何より。
今日は日曜だというのにこれから仕事である。
■ リハーサル中止
今日行われた探査機「はやぶさ」のリハーサル降下が中止された。午前中は順調に降下していたのに仕事から帰ったら「本日の降下中止」のアナウンスで少しがっかり。
「GO/NOGO判断の際に異常を検知したたため中止となりました」って、何があったんじゃー、とか思ってたんだけど、やっと情報が出てきた。
要するに自律航法システムが目標を見失ったって事らしい。
うーん、探査機に搭載されてるコンピューターって処理速度が遅いからなぁ。なにしろ20年前のパソコン程度の性能しかないんである。むしろこれで自律航行できる方が驚きなのだ。地形が複雑になると対処しきれなくなるのかなぁ。
近距離用の距離測定装置のテスト
ターゲットマーカー(目標地点をレーザーで確認するための反射鏡)の投下
10センチ程の小さな探査ロボット「ミネルバ」の投下
が予定されていたけれど、全て中止。残念。
2つの姿勢制御装置が壊れた時にはもうだめかと半分諦めたんだけど、関係者は諦めなかったのだね。頭が下がる。
この諦めない姿勢でなんとか次のテストや本番にも挑戦して欲しい。
特に探査ロボットは何とか投下して地表の岩質を見たいもんだ。
幸い懸念されていた燃料はもう一度リハーサルを追加する分くらいは残っているらしい。
いずれにしても計画の練り直しなんだけど帰還軌道の関係で12月の頭には「イトカワ」を離れなければならないらしい。その間にNASAの地上局が使えるかが問題ってのも何だかなぁ。
どんな衛星を作っても結局運用はアメリカの都合次第ってのも情けない話しではあるぞ。
9月にはランデブー飛行に入って詳細な情報を送って来ていた。
最新の画像を見ると、1メートル以下の小さな岩まではっきり見えて、よくぞここまで、なんて思っちゃう。今回、中止したとはいえ500メートルの距離までは近付いたんだから更に高解像度の写真も撮影されているはずで、公開が楽しみ。
でもこれ、本当に砂糖をまぶしたカリントウのようだ。粒々の小さな岩がへばり付いてる。
小惑星って言うとでっかい岩石のような、ジャガイモのようなイメージが有ったけれど、表面を詳細に見ると実際はかなり違うものなんだな。
月の様に重力が強くないから近くの小天体を引き寄せても激突してクレーターにならずに形が残って堆積してるって事だろうか。
逆に言えば簡単に引き剥がされて飛び散って新たな小惑星が作られるって事にもなる。これはこれで驚きだ。
この後、二度の着陸(といっても滞在時間はほんの1秒か2秒なんだけど)とサンプル採集が上手くいく事を願うばかりだけれど、それより何より、ここまでの成果が上がったんだから無理をせずに必ず帰って来るんだよ~。







