'!' は論理演算子 Not です。
「日記にあらず」と読んでください。
■ 蘇生
昨年末から通信が途絶えていた小惑星探査機「はやぶさ」との交信が回復したもよう。まずはめでたい。
だけど今の通信レートが32bps ってのがなんか「瀕死ー」って印象だよ。
これでも1ビットや8ビットよりましだけど、一秒間にたった4バイトのデータしか送れないんだものなぁ。漢字にしたら2文字ぶんですぜ。ネットの回線が遅いなんて文句言ってたらばちがあたるよ。
1月末にはビーコンを受信。意外と早い回復だったようだ。ただし、完全に電源が落ちて、極低温にも曝されたのだろう。ダメージも大きいようだ。
コンピューターがリセットされた訳でタッチダウン前後のデータも消滅したもよう。研究者にはこの辺が一番痛かったかも。
12月の時点で姿勢制御ロケットの燃料(ヒドラジン)が機体内に漏れていたのだが、その後、酸化剤(四酸化窒素)も漏出したらしい。これ、混ざっただけで発火するっていう性質があって、エンジンの構造を単純に出来るからスラスターに使われてるんだけど、よく機体内で発火しなかったものだ。不幸中の幸いっていうか、奇跡に近いんじゃないの?
バッテリーは内部のショートで使用不能。スラスターも燃料が無くて使えない。
電力は太陽電池で賄えるそうだが、姿勢制御も兼ねることになったイオンエンジンを再始動できるかが問題。
これから時間を掛けて内部温度を上げ、ゆっくりと機体内部に残ったガスを追い出してからエンジンのテスト。ハードルは高い。帰還できれば本当の奇跡だ。
でも、その奇跡を祈っちゃうぞ。
それにしても技術的な説明を読んでると「すげーなぁ」って思う。
残っているイオンエンジンの中和剤は僅か42~44kg。これで上手くいけばだけど3億kmの距離を戻ってくるんだから(いや、地球をかすめて行くだけだけど)、すごい燃費だよなぁ。
もっとも中和剤のキセノンガスは42kgで700万円ほどするそうだが。
■ 黒鮫号
いや、「黒鮫号」やっと公開である。だらだらしている間に緯度0のDVDが発売されるというオマケがついてしまった。
用意したキャプションも書き直し。
作品そのものは半年以上前に完成していたのだが、解説のページを作るのにえらく時間がかかってしまった。
っていうか、形が出来てからモチベーション下がりっぱなしだった。
それに加えて今回は長短合わせると全部で18ページっていう、私としては前代未聞の量にうんざりしてしまった、というのが実感。
何もここまで説明しなくても「これを作るスキルがある人なら出来るだろ」とも思うのだけど、つい心配になってしまうのである。
ガラモンを作るのに1年。今回は2年でなんとかモノになった。
次は3年掛かるか4年掛かるか。
いくら寡作といっても程度の問題でしょう。
もう少し並行して作ることも考えないとねぇ。
でも性格的にそれができるか否か...
■ 東宝自衛隊
最近、トンズマさんという方とメールのやり取りをしていて、やはりペーパークラフトを趣味にしておられる方である。それも「東宝自衛隊」を紙で作ってしまわれたそうな。
東宝自衛隊といえば現実の自衛隊の装備をベースにSF的超兵器を加えた、怪獣映画ファンには特別な組織である。
タダの自衛隊ではない。
自衛隊が使っている現実の車両に目玉的なメカが加わって何ともリアルな世界が構築される。
その車両群を作ってしまったという。これは見たい。
作品の写真など撮ったことがないというトンズマさんに、無理にお願いして写真を撮って頂いた。
いやー、これが凄い。
「メーサー車」や「Aサイクル光線車」も圧巻だが、それを取り囲むトラック、戦車や照明車まである。これは本当に「東宝自衛隊」である。
こうなると私の要求もエスカレートして (^^; 今度は日記で紹介させて! となってしまった。これを秘匿しておくのはあまりにもったいない。
っというわけで、トンズマさんの承諾を得てここに写真の一部を掲載させて頂く。
まずは下の写真をクリック。
 |  |
 |  |
 |  |
これだけ並ぶと壮観である。Aサイクル光線車の車列を見ていると伊福部マーチが聞こえてくるぞ (ToT)
これ、何が良いかといえば作り込みの加減が絶妙なんである。
メーサーとかAサイクルを見ると非常に細かく作りこんであるのが分かる。
だけど「頑張れば作れるんじゃないの?」と思わせるシンプルさも持っている。
私がペーパークラフトを始める前だからよく知らないのだけれど、かつてゼネラルプロダクツというメーカーから超精密なキットが出ていたらしい。だけど...これ、作りたいって思う人が何人いるだろう。(やっぱ作ってもらってなんぼだよなぁ。って、作りにくい作品ばかり公開してる私が言うのも何だけど)
これと比べるとトンズマさんの作品は精密さという点では多少歩が悪いけれど、作る労力と完成後の見栄えの比率(何ていうかコストパフォーマンスみたいな)では決して負けないと思う。
そして題材としては地味なため今まであまり造る人がいなかった旧式の大型トラックやジープなども、ここでは立派に役割を果たしている。簡単かもしれないけどたくさん無くちゃね。数は力なり。
次はF-86・セイバーを作られるそうである。うん、航空自衛隊だって重要だ。
願わくばいつか、ぽんぽん砲や61戦車も見たいです。
現在、トンズマさんはホームページをお持ちではないそうだけど、ぜひ開設して展開図を一般公開してほしいなぁ。
■ ああ、伊福部昭が亡くなってしまった
朝、ネットをチェックしていたら作曲家の伊福部昭氏の訃報が目に飛び込んできた。直腸ガンによる多臓器不全だそうである。
さすがに91歳という御歳だから天寿を全うしたと言ってよいのだろうが、ファンという以上に、敬愛する方の死去というのは黒澤明監督以来のショックである。
名も無いファンの一人ではあるが、哀悼の意をなにか形で表せないかとトップページのロゴをモノクロにした。
私が伊福部昭を知ったのは当然ながら怪獣を中心とした映画音楽からである。
力強く繰り返されるあのリズムと日本的旋律は私の中で特別なものだった。
そして、いつの間にか映画音楽に留まらず、氏の音楽そのものを愛するようになっていた。ストラビンスキーのように力強く、それでいて日本的な、それも妙に風雅ではなく(いや、風雅な曲もあるけど)土着的な、地に根の生えた生命力にあふれる響き。
特に好きなのは大編成のオーケストラを中心とした交響曲である。
映画音楽では編成の小ささや演奏時間の短さで不満が残ることもある。ああ、この音の渦にもっと浸っていたいのに。
そんな不満を満たしてくれるのが「リトミカ・オスティナータ」や「ラウダ・コンチェルタータ」や「交響譚詩」だった。
氏の曲が掛かると演奏会に足しげく通った時期もあった。
「ラウダ・コンチェルタータ」の初演を聴いたのが自慢でもあったし、「SF交響ファンタジー」の公開録音にも行った。(懐かしい! 故、平田昭彦氏が司会を勤められた。)
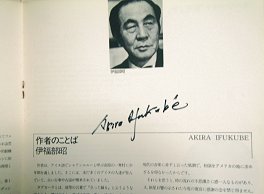
私の持っている唯一の有名人のサイン。
私はあまり物を大切に取っておく方ではないのだが、それでも演奏会の合間にロビーで一人所在無げにしていた氏からプログラムに書いて頂いたサインは数少ない宝物の一つである。
ああ、またひとつ巨星が堕ちてしまった。
合掌である。
■ 今更だから「三丁目の夕日」
原作に関しては連載が始まった当時はかなりはまってた。ぽわー、っとしたムードで悪人が一人も出てこない、なんてのは割と好きなタイプのお話だったから。でも、そのうちキャラクターの平板さに飽きたのか、泣かせにあざとさを感じてしまったのか、とにかく読むのをやめてしまった。似たようなマンガの「じゃりん子 チエ」にはずっと付き合ったのに、何処が違うんだろう。って、それは別の話。
で、映画の方はそのキャラクターをかなり大胆にアレンジして、原作の味を残しつつ「映画」として良くまとめてある。六ちゃんを女の子にしちゃうなんてのはライトオーバーのクリーンヒットだ。細部にまで行き届いた映像作り。きめ細かな演出。ゆったりと時間が流れる脚本。ぴったり役にはまった出演者。
これらの映画としての要素がパーフェクトであると認めた上で、この映画の最大の売りでありキーワードの「昭和レトロ」と言うことになる。
ネット上の感想を読むと、当時を知る世代だけではなく、その子供の世代までも、「自分は知らないけど懐かしい」という感想が多い。
古いものを見て「古い」と思うか「懐かしい」と思うかは個人の感性の問題である。きっとこれは懐かしいと感じられる人だけが楽しめる映画だと思う。
そして、私は何故か「新しい」と思っちゃったんである。
そろそろ上映も終盤だと思うので書いちゃうけど、以下、ネタばれ、突っ込みなので、これから観ようとか、この映画をこよなく愛する人は読まないでください。
と言うわけで伏字の部分はドラッグ、反転で。
冒頭、子供たちが飛ばすゴム動力飛行機が高く舞い上がって当時の町並みを俯瞰するシーン。これは観客を映画の世界に引き込む重要なシーンである。セット撮影と見事なCGを上手く繋げて、かつてなら絶対に出来なかった自然な昭和の映像を再現してくれる。
でね、かつてはゴム動力ヒコーキ大好き少年だった私は飛ばす前に思ってしまうのですよ。
蛇足だけど付け加える。
そして子供たちがはしゃぎながら飛ばすところ。
「小学生があんなに綺麗に作れやしないよ。」
茶川先生の駄菓子屋の店頭に在ったから売ってた物を買ったんだろって突っ込みがあるかも知れない。
断言する。それは在り得ない。
確かにゴム動力飛行機を売っていた記憶はある(もう少しだけ後の時代の記憶だけれど)。でも、それは翼長30センチほどのオモチャの飛行機だ。
あれは「B級競技用」という本格的なライトプレーンだ。大多数の小学生が挑戦して挫折したはずである。今みたいにガンプラの完成品ですらお金を出せば買える時代じゃない。
その昔は自分で竹ひごをローソクであぶって曲げていたのが、始めから曲げた竹ひごが入ったキットを売っているだけで「すごい!」時代だったのだ。
今で例えるなら、そうだなぁ、町の中古自動車屋でF1...とまでは言わないけれどFJ1600のフォーミュラーカーを売ってるかい? って感覚である。
店頭の細長い袋に入ったキットすら昭和33年に売っていたか怪しいものだ。
「おい、そんな道端で飛ばしたら失くしちゃうだろ。」
当時、町並みは低かった。どこかの家の屋根に落ちたら二度と見付からないので、大事な飛行機を、ましてよく飛ぶ飛行機ほどそんな所では絶対飛ばさない。
まず「つかみ」で躓いてしまった。そんな重箱の隅を突付くなよと言われても生活実感だから仕方がない。でもここまではありがちなシーンだから許した。
決定的に「???」と思ってしまったのは重要なアイテム、「ミゼット三輪車」。これは原作でも重要なイメージキャラクターとでも言うべき象徴的なアイテムだから外すわけにはいかないのは理解できる。だから少し位のことは許す。
それにしたって昭和33年にあんなガタガタのミゼットは無いだろ!
確かにミゼットは汚れたポンコツのイメージが強い。しかし、よく考えればそれは後の時代に植えつけられたイメージなのだ。そういえばあの「新型ミゼット」、幼い頃はカッコいいと感じていたのを思い出した。
更に突っ込みは続く。この映画、時代が特定されているように、ある程度土地勘があれば場所もかなり特定できる。東京タワーの左に山が見えるから東京タワーの南側。
それはいい。でも三田から高円寺まで、都電を乗り継いで子供だけで行けるか?
>あのころ、あの辺りで育った子供にとって渋谷駅を越えるのは、ほとんど外国に行くほど大変たったと思います。
ただし、ショウちゃんさんはこれを大冒険としてリアリティーがあって良いと述べられているが、私は、逆に無理だろー、とか考えてしまったのだった。少なくとも乗り換え路線が分からないだろう。
もう一つ、私は当時の都電なんて殆ど知らないからあまり自信が無いのだけれど、私の覚えている横浜市電の最も安かった運賃は大人10円、子供5円である。
当時の都電の運賃をネットで調べたけれど、明確な答えが見付からなかったが昭和31年頃、13円?という情報があった。とすれば子供は7円。
どうひいき目に見ても10年以上は使ったポンコツだ。昭和40年代には在りがちだったけど、どんなに乱暴に扱っても発売されたばかりで、あそこまで錆びる機械はないぞ。
汚れすぎ(ってか、汚しすぎ。当然意図してそうしたのだろうから。)。
ちなみに、ミゼットがいつ発売されたのか調べてみた。そうしたら丸ハンドルで二人乗りのタイプが発売されたのは昭和34年であった。当時はバーハンドルの一人乗りしか無かったのだ。
原作では正確な年代に関してはぼかしてある。大体30年代の前半から中頃のイメージだから問題は無い。(それにしてもあんなには汚れてないけど)
しかしこの映画では建設中の東京タワーやフラフープで明確に昭和33年と規定しているのだ。だから首をかしげてしまう。
私はそれほど土地勘も無いので田町か芝浦あたりかと思ったが、「ショウちゃんのエーガな日常」というブログで地元の方が三田と推測されている。なるほど。まあ、田町駅の前はすぐ三田だから私の推測も大きく外れたわけではない。
ショウちゃんさんも指摘されるように
10秒で済む。車掌に
「高円寺に行くにはどこで乗り換えたらいいんですか。」
「え!?、君たち高円寺まで行くの?」
なんて聞くシーンがあれば納得したかもしれない。
子供たちが手にしていたのは15円。それなら往復できるだろ、と疑問をもってしまったのだ。
一応書いておくと、当時は都内なら何処まで行っても、何度乗り換えても料金は同じ。
一度降りて別の路線に乗り換えるとき、目的地は自己申告という今では信じられない、おおらかなシステムだった。
っと、まあ、いろいろ突っ込んだのだけれど、
テレビや冷蔵庫が来たエピソードなと、少々カタログ的な感が無いでもないが、全体としては細部にこだわって非常によく昭和を再現している。
よく再現しているがゆえに、以上のような実感と微妙にずれる部分がリアルな風景と相まって妙な現実感を生む。
この妙な現実感が、昭和に作られた昭和の映画ではないのにリアルな昭和の風景という、更に理解できない「新しさ」として感じられるのだった。
新しい映画だから(つまり新作だから)「新しい」のは当然なんだけど、この「新しさ」が、少しだけ居心地が悪いと感じたのだった。
それにしても後半、ちょっと泣かせ過ぎで逆効果じゃないかい?
泣かせるのは中盤にちょっと、終盤にしんみりってのが一番余韻が残るような気がするんだけど。
■ 日本だから汚い
新年早々、少しばかり気分が悪い。
しばらくチェックしてなかったのだけれどガラモンのページにある7枚の画像すべてに直リンされてた。韓国のサイトである。
画像を持って行って勝手に使う分には何の不満もないけど、向こうのページを開くたびに、こちらのサーバーへ直接アクセスされるのはかなわない。一枚くらいやられるのは時々あるけど一度に7枚はやりすぎだろ。
頭にきたので、すべてのファイル名を変えて表示されないようにしたのだけれど、作り方のページを機械翻訳してダウンロードできるようにしたり、好意で紹介してくれてるようだから考え直して小さくて軽い画像を作って残しておいた。
それだけで気分が良くないけど、まあ、それはいい。
そこは掲示板かアップローダーのようなものらしくて、何人かのコメントが付いているので訳してみた。
ウチへのアクセス元を辿ると外国ではアメリカや台湾が中心なんだけど、少数ながら意外に広範囲で、中には何語だかわからないサイトもある。ロシアのサイト経由でのアクセスまであるのに韓国と中国のホストからのアクセスは皆無だった。
これはペーパークラフトを作らないとか怪獣を知らないとか、文化の問題だろうと思っていたのだけれど、最近韓国からは翻訳サイト経由でぽちぽちとアクセスが来ていたのだった。(多分ウチへの直接のリンクではなく翻訳サイト経由のリンクが存在するのだろう。翻訳サイトが擬似的にプロクシの役をするのでアクセス元は見えなくなる。)
だから彼等がガラモンを見てどんなふうに感じるのか興味を持ったのだ。
この画像をリンクした本人のコメント。
お互い機械翻訳だから言葉の意味を吟味する必要がある。
「いやらしい」という表現は多分「グロテスク」とか「気持ち悪い」とかのニュアンスの言葉を機械が勝手に置き換えたものだろうと想像する。
そして以下のコメントでは「いやらしい」に代わって「汚い」という言葉が続く。
この「汚い」の元の言葉のニュアンスがどういうものか解らないが、より拒否的な意味合いを持つことは想像に難くない。そして戸惑いと言っていいコメントが続く。
ずっと日本映画やテレビ番組が禁止されていて、怪獣を愛でる習慣のない人々が初めてガラモンを見て気持ち悪いと思うのは悲しいけれど正常な感覚だと思う。いや、我々だって子供の頃は怖かったし、製作者の狙いでもあるわけで。そんな中で
そうではないんでしょうか? 私だけ変な良い人になるのか
なんてコメントがあるのは救いでもある。
でもね、
>どこで出るんです???
ここは韓国の「2ちゃんねる」か?
私のペーパークラフトの出来を否定するのは勝手だ。でもこれは怪獣文化に対する全否定だ。
私自身、好きか嫌いかは別にして韓国の文化を否定するつもりはない。それは韓国人のみならず韓国好きの日本人の人格をも否定する行為だから。
日本にも同じ様な発言をする人間は幾らでもいるからお互い様なのだが、直接自分が関わる場所でこういう言葉を目にすると非常に印象が悪い。
厨房の戯言として無視するしかないのだけれど、こんな草の根的な部分から隣国との関係が悪くなって行くのは好ましくない。
PHPの動的なページなので「正しいアクセスの仕方」が分からないのでリファラーの一つを張っておく。
当該サイトの掲示板担当の方から丁寧なコメントを頂いた。(下記コメント欄参照)
ご迷惑が掛かるといけないのでリファラは削除した。
関係ないけどテレビなんかでよく日本通の外国人に「納豆は好きですか」なんて聞くレポーターや司会者がいるけど、あれってすごく失礼で恥ずかしい行為じゃないか?
何か納豆を食えることを日本好きの尺度を計る踏み絵のように使ってるようで腹立たしい。正に村社会的発想だ。納豆は日本の食文化だし私も好きだけど、それを好きか嫌いかは個人の嗜好の問題だろ。納豆を食えることが友達の条件なのか?
去年の暮にはこのページに毎日 200以上の怒涛のスパム攻撃。下手したらサイトの一日のアクセス数より多い。一時的にコメントとトラックバックの受付を閉じなければならなかったほど(現在はほぼ復旧したが、コメント欄にURLを書き込むとエラーになる)。別にコメントもトラックバックも無いから問題ないのだけれど門戸を閉じちゃうのは心苦しい。こちらからコメントやTBすることもあるからギブアンドテイクの原則に反する。
まあ、少し良いことが無いでもない。
松浦さんが下の記事の「一部」に反応して一本記事を書いてくれた。単にネタを提供したってだけだけどね。
あとは掲示板のスパム対策強化。ついでにメールアドレスを書いてもアドレス収集ロボットに拾われないようにしときました。
本当は PHPを使わず出来る対策を一つ思い付いたので、此処のスパム対策をしたいんだけど、時間がない。そのうちに。
年が明けたら掲示板への電波が強力になったので電磁シールドを張る。
何で更新もしないで維持してるだけのサイトにこんな労力を使わなければならないのか。外部の声を遮断して自閉的なサイトにするのは簡単だけど...少し鬱。
愚痴ばっかですいません。
■ 科学技術部記者のなれの果て
えーっと、ココの所ずっと暇があると「はやぶさ」関係をヲチしてるわけだけど、今回はちょっと別の角度からの話。
日経の清水正巳という編集委員のコラム。
研究の失敗に寛容な風土はできるか
掲載直後から2ちゃんねるの関連板あたりで批判が相次いで、遂に今この問題ではネット上で一番影響力のある松浦氏も噛み付いた。
件のコラムに関しては何の勉強もせずに思い込みだけで書いた記事で、読んだ直後は本当に頭に来たが、もう納まった。私の言いたいことは多くの方がいろんな処で突っ込んでいるから。 あ、これだけは書いておこう。
外国のES細胞捏造なんかと同列に語るな!
これが日経の編集委員で「日経サイエンス」の元編集長ってんだから情けないやら悔しいやら。
随分と昔、これと同じ思いをしたことがある。
発行部数、日本一の某大新聞の署名入り記事で「日本は基礎研究より応用研究に力を入れるべきだ」という論旨の記事を読んだとき。
それまで「日本は研究の成果の美味しい所だけを持って行ってしまう」と海外から批判され、外国が研究の成果を渡してくれなくなってギブアンドテイクじゃなきゃだめだと、やっと基礎研究の重要性が一般にも認知され始めた頃だ。にもかかわらずこの某大新聞は貴重な紙面を割いて「基礎研究はいらない」と言い張る記事を掲載したことに暗澹たる気持ちにさせられた。
小さなコラムとはいえ全国の人が読む新聞だから影響力は否定できない。なるほど、と納得する人も少なくはないだろう。
対して反論する場所はどこにもない。せいぜいが頑張って投書する位だが、それで記事が取り消されることはない。
ところが今回の件に関しては松浦氏も書いておられるように
という事だろう。
民主主義が(うまく機能すれば)政治家や役人が「お上」から「市民の下僕」になる様に、ネットによって情報も民主化されつつあり、メディアの人間も特権階級ではいられなくなっているってことにこの清水某は思い至らないから安易な思い込みを書いたわけだ。
ブログは簡単に炎上するが新聞社のサイトは耐火構造になってるから(^^)燃え落ちることはないだろう。
しかし、このコラムもいつかは削除される日が来るが、ネット上で大量に書かれた批判記事の幾つかは残り続けるだろう。今現在でも「清水正巳」と検索すれば本人の記事より松浦氏の記事が先に表示される。
ネットを見る人は、まず批判記事を目にしてから清水某の記事を読むわけだ。
蛇足だけれど、民主主義ってのはすごく危ういバランスの上に成り立ってる。
「十二人の怒れる男」のラストシーン。陪審で少年の冤罪を晴らしたヘンリー・フォンダか誇らしげに言う。「だから民主主義は素晴らしいんだ。」
でもね、もしその場にあんたが居なかったら民主主義で少年は死刑になってたんだよ。
陪審員の中にいつもヘンリー・フォンダがいるとは限らない。
ネットだって誘導を間違うととんでもない事になる。
ってことで、ウチも松浦ブログにトラックバック。え?縁起モノですから。
■ 危篤
今日のテレビは一日中「耐震強度偽装事件」の証人喚問。姉歯某。自己保身のためのファウルは誰でも大なり小なり犯す可能性はあるし、下請けの悲哀が解らないではないが、自分と家族の生活を守るために何百、何千の人の命を危険にさらしたことの言い訳にはならない。
それより何じゃい、あの議員の質問は。お前の意見なんか聞いてない。選挙演説じゃないんだからさっさと質問しろよ。
そんな中、昨日から待っていた「はやぶさ」関連の記者会見。勿論テレビ中継があるわけじゃ無いから「松浦晋也のL/D」だけが頼り。朝から何度もチェック。
上の記事が出る前に速報。うわぁ、だめか...
幾つかの新聞社のサイトを見る限り帰還予定が2010年に延期と云った見出しだけれど、記者会見の様子を見ると現状は、医者も手を出せない意識不明の危篤状態という感が強い。
電源が落ちてビーコンすら受信できない。地上からのコマンドも受け付けないほど姿勢を乱して回転している。
今出来るのは回転モーメントが減衰して姿勢が安定するのをじっと待つだけ。その時太陽電池パネルが反対を向いていたら...電力が回復しないで...って読めるわけだけど、確率の問題ってそういう事ですか?
確かに復旧の可能性が3分の2なら悪くはない。でもその先に待ってるのはもっときわどい運用。
スラスターが復旧しなければイオンエンジンの中和剤として積んでるキセノン噴射で姿勢を制御して帰還軌道に乗せるって超裏技。これ、車で言えばハンドルが壊れたからアクセルとブレーキでスピンターンを繰り返しながら目的地に向かうようなものだ。
つまり
可能性がある限り諦めない。この姿勢には頭が下がる。
でも運用チームの皆様、この一ヶ月へとへとだと思います。今はゆっくり休んで鋭気を養って頂きたい。
そして必ず地球圏への帰還を果たして欲しい。気長に待つとしよう。
さて、気を取り直して与太話。
この数回の記者会見の中で度々登場する「みそすり運動」って言葉。
コマの回転が落ちてきたとき大きく首を振るような動作のことなんだけど、いやー、久々に聞きました。いや目にしました。今でも使ってるんだなぁ。
初めて聞いたのは子供のころ。多分地軸が長い時間で移動するのを説明する教育番組か何か。その頃、すでに「随分古い言葉だなー」って思った。我々の世代ならやったことは無くても辛うじて「味噌を擂る」の意味を理解できるけど(それにしても「胡麻を擂る」方がまだ身近だったな。「日本一のごますり男」とか)、今の子供には何の事やら理解できないでしょ。
よほど酔狂じゃなければ自家製の味噌なんて作らないし、すり鉢だって滅多に無いよ。
こういう意味不明の言葉は解りやすい言葉に置き換えるのが良いのか、昔の生活を伝えるために残すのが良いのか?
でもロートルには「コーニング」よりは解りやすいんだけどね。
■ クレーム
という訳で昨日の続き。スズキのお客様相談センターに電話して状況を説明する。
「ペダルが横に動くんです」と伝えると「え?!」と絶句。
暫くして購入したディーラーから電話。また説明。
「とにかく見てみないと分からないので通常の修理としてお預かりします。」
「ってことは有償ですか?」
それならウチで修理するわい。自分で直せば100万キロ走っても割れないようにしっかり溶接できるし。
問題は運転中に急にクラッチが切れなくなったことなんだから。で、更に問題なのがブレーキぺダルも同じ構造ってこと。たまたま部品の製造ミスなのか、本質的な強度不足なのか、そこをはっきりさせたいのだからクレームとして上にあげてもらわないと困るのだよね。
「それなら消費者センターとか、然るべきところに相談しようと思ってるんですけど。」
これは効いたみたいだ。実は昨夜義弟にアドバイスしてもらったんである。
「分りました。とにかく上司と相談しまして一両日のうちに...」
「毎日使ってるんだから急いでください。もし時間が掛かるなら代車をお借りしたいのですが。」
「えーと、今、代車が無いんですよ。」
「それならとにかく早くしてください。」
うーん、出来るだけ高飛車な感じを与えないようにソフトな口調で言ってはいるんだけど、これが逆の立場だったら嫌な客だよなぁ。まあしょうがない。相手のペースに乗ったらうやむやにされちゃう。
そんな、こんなで夕方には代わりの軽自動車をトラックに積んで引き取りに。
ブレーキもしっかりチェックするように念を押したけど、ちょっと頼りなさそうなアンチャンだ。大丈夫なんかい。それに部品を交換したら外した部品を見せてね、と。
で、代車が無いから他の店から借りてきたという車。
当然ながらオートマチック。困ったな、マニュアル車ばかり乗ってるから運転に不安がある。ついシフトレバーに手が伸びて動かしそうになる。
その上ピカピカの新車じゃないか。試乗車を持って来たのか?
運転席以外のシートにはビニールが掛かって、マットは汚さないように新聞紙が敷いてある。
こんなの仕事には使えないよう。
油で汚れても弁償できないぞー。
■ 溶接不良
急に車のクラッチペダルが効かなくなった。営業車、兼乗用車として使っている10年物に近いスズキ・エスクードである。
我が家では昭和生まれで老衰寸前の軽自動車(スバルサンバー・同じく老衰寸前の父親が主に使用)と、石原某のゴリ押しで来年で使えなくなる日産の2tトラック(いすゞのOEM)の3台の老朽車を使ってるんだけど、一応これがメイン、っていうか下駄代わりなので壊れると困るのだ。
ペダルがグラグラと横に動く感じがするので調べてみると軸受けの溶接が割れている。
普通に考えればペダルをアッセンブリで交換すれば直るのだけれどウチも機械屋、自分で溶接し直せばOK...なんだけど、これ、奥なんで外すのが大変。
見れば構造は判るんだけど、シャフトと戻し用のスプリングはともかく、一番奥にあるクラッチワイヤーを外せるか?
いや、外した後付けられるか?
こういうのはやっぱり経験なんだよね。素人でもできないことは無いけれど慣れないとものすごく時間がかかる。どうしようか。
ところで、走行距離8万キロでペダルの溶接が割れるってどうなんだろう。
場合によっては事故につながりかねない場所ではあるし、溶接不良か強度不足も考えられるよなぁ。機械を知ってる身からすると使用期間も考えて微妙なんだけどクレームで処理できるんだろうか。
って言うかクレームを出した方がいいんだろうか。
というのも数日前、似たような修理をしたばかりだからなんである。
もちろん車じゃなくてホンダ製のクローラの運搬車なんだけど、ギヤが入らないから修理してくれという依頼で、見るとシフトレバーのステイの溶接が割れていた。
部品の在庫があったから交換してその場で直った。多分この近辺でこれをその場で直せるのはウチだけだろう。お客さんにしたら「すぐに直って良かった、良かった。さすが専門家!」ってことで大感謝された上に修理代も頂けるから本来なら気持ち良い仕事のはずなんだけど、実はちょっと後ろめたい。
素人目には溶接が割れるのは無理して使ったからと思えるかも知れないけど、割れ方を見ると明らかに溶接の不良なんだよね。肉は盛ってあるけど溶け込み不足。だからポロンと取れちゃう。芋半田と同じ理屈。要するに製造ミス。だけどお客さんにそんなこと言えないんである。
メーカーにクレームを出しても交換部品は送られて来るけど作業工賃や出張料は販売店持ちが普通。つまり仕事をしてもウチは一銭にもならない。保障期間が過ぎてても不良は不良だろ、と言いたくなるんだけど。
まあ、一般消費者が関与しない産業用機械なんてこれが実態ですよ。
あ、ホンダさんの名誉のために一応書いときますが、以前下請け工場の製造ミスで部品の取り付け方が間違っていて故障したときは(明確な製造ミス)、ちゃんと全ての費用を出して頂きましたですよ。これはメーカーとしては異例と言ってもいい。
ってわけで判断に迷ったので日産で設計をやってる(つまり車の専門家だ)義弟に相談してみたら、かなり厳しい答えが帰って来た。まあ、ライバル会社ってのもあるかもしれないけど業界の常識としての答えだと思う。
曰く、
今回はクラッチペダルだから良かったが同じ構造のブレーキペダルなら命にかかわる。
拠って(出来るからと言っても後の保障に関るので)自分で修理してはいけない。
更に持ち込みはせずに引き取りに来させて、その間代車を要求せよ。
応じない場合は消費者センターなど、しかるべき処と相談するべき。
とのことである。
なるほどねぇ。逆にメーカーサイドからしたら厳しい世界ではあるな。
明日ディーラーに連絡してみよう...。
話は変わって「はやぶさ」
満身創痍、刀は折れ矢は尽き、遂に竹槍で突進する状態。
「はやぶさ」探査機の状況について ... JAXA プレスリリース
14日以後に「イトカワ」を出発する予定らしい。そのときにもう一度書きます。
予定は未定 (T_T)
Page:
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]







